こんにちは、およげないペンギン、ぺんぎんママです。

夏休みの宿題のラスボス的存在、「自由研究」。
お子さんの今年の自由研究テーマはもう決まっていますか?
自由研究はテーマ選びがまず最初の難関。
工作系・観察系・実験系などいろいろなジャンルがあり、学年や興味関心によっても取り組み内容は大きく異なります。
1日でさっくり完了できるものから、夏休みの期間大半を使って取り組む大作まで、向き合い方もさまざま。
わが家にも小6の子どもがいるので、前回は理科を題材にした小学5、6年生向けのおすすめテーマ5選を紹介しました。
今回は社会のテーマで5つ考えてみました。
学校の授業で学習した内容で近いものがあれば、関連させて学びを深めるのもよさそうですね。
参考になれば幸いです。
小学校高学年 自由研究テーマ 社会編
地域の歴史を探る
自分の住んでいる地域の昔の生活や文化について調べます。
「京都」「大阪」などの広めの地域で調べてもいいし、小学校区くらいの狭い範囲に絞るのもアリです。
両親や祖父母が昔からその場所に住んでいたなら、昔の話を聞いてみるのもいいですね。
イラストや写真を使って分かりやすく発表するようにしましょう。
調べる内容の例
- 自分の住んでいる町や学校の歴史を調べる
- 古い地図や写真と現在の同じ場所を比べてみる
- 昔からある建物や場所、地名の由来について調べる
- 地域のお祭りや伝統行事について調べる
まとめ方の例
- 過去と現在を比較し、街がどのように変わってきたのかを写真や年表でまとめる
- 地図に昔の建物の位置や地名の由来などを書き込んで、オリジナルマップを作成する
身近な商品の流通を追う
流通について調べると、商品が私たちの手元に届くまでにたくさんの人が関わっていることが分かると思います。
可能であれば、お店の人に話を聞いてみてインタビュー内容をまとめてみてもいいかもしれません。
感謝の気持ちが伝わるまとめ方ができるといいですね。
調べる内容の例
- スーパーで売られている身近な食品が、どこで作られてどのようにして自分たちの食卓に届くのかを調べる
- 食品以外の商品がどのように作られて販売されているのかを調べる
- ネットショッピングで商品がどのように届けられるのかを調べる
- 商品のパッケージに書かれている産地や製造元を確認する
まとめ方の例
- 商品の「旅」をテーマに、産地からお店までの流れをイラストや写真でまとめる
- 様々な商品の流通経路を比較し、それぞれの違いや工夫を表にまとめる
ゴミ問題とリサイクルについて考える
小学校の学習でもSDGsや3R(リデュース・リユース・リサイクル)について学習する機会が増えていると思います。
その中でも身近に取り組みやすいテーマ、「どうすればゴミを減らせるか」を考えてオリジナルの解決策やアイデアを発表します。
プラスチックゴミや食品ロスなど、特定のゴミに焦点を当てて深掘りするのも面白いですね。
調べる内容の例
- 自分の家や学校から出るゴミの種類や量を、一定期間記録する
- ゴミの分別の仕方や、地域のゴミ収集のルールについて調べる
- リサイクル工場や清掃センターでゴミがどのように処理されているか調べる
まとめ方の例
- グラフや表を使って、ゴミの量の変化や内訳を分かりやすくまとめる
- リサイクルの流れをイラストや写真で解説する
- 自分の家庭から出るゴミの量や種類から、ゴミ削減のために自分たちができることを考えて提案する
身近な税金を知る
「税金」と聞くと子どもには関係ない、と感じるかもしれません。でも子どもも買い物をすると「消費税」を納めていますよね。
いろいろな種類の税金があることを調べて、わたしたちの税金が身近なくらしの中でどのようなことに使われているのかをまとめます。
調べる内容の例
- 買い物のレシートを集め、自分がどれくらいの消費税を払っているかを調べる
- 消費税以外にも、家や車にかかる税金、たばこ税、酒税など、様々な税金があることを調べる
- 自分の家ではどのような税金を納めているか保護者にインタビューする
- それぞれの税金が、どのような目的で使われているかを調べる
まとめ方の例
- 自分がおこづかいやお年玉で買い物をして1年間で払う消費税の額を計算してみる
- 税金がなかったらどうなるかを考えて、税金のない社会の問題点をまとめてみる
- 自分が使っている身近なもの(学校や公園、道路など)にどれくらいの税金が使われているかを調べてイラストや地図にまとめる
- 「もしも自分が市長になったら、どの税金を何に使いたいか」を考えて、オリジナルの予算案をたててみる
地域の「ユニバーサルデザイン」を探す
ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、文化の違いや障がいの有無に関わらず、誰にとっても分かりやすく使いやすいように工夫されたデザインのこと。
自動ドアや段差のない出入口のようなものから、シャンプー・リンスのボトルや文房具のような日用品まで、さまざまなところにユニバーサルデザインが使われています。
身近にあるユニバーサルデザインを探して、それがどのようなかたちでどのような人の役に立っているのかをまとめてみましょう。
調べる内容の例
- 公園や駅、お店など、身近な場所のユニバーサルデザインを探す
- 点字ブロック、多目的トイレ、音で案内する信号機など、どんな工夫がされているか、なぜその工夫が必要なのかを考える
- 家の中にもユニバーサルデザインがあるか探してみる
まとめ方の例
- 「みんなにやさしいまちのヒミツ」「こんなところにもユニバーサルデザイン」など見出しをつけて新聞記事のようにまとめる
- 実際に撮影した写真とともに、見つけたユニバーサルデザインを紹介する
- 誰のために、どんな目的で作られたのかを解説する
- 新しいユニバーサルデザインを考えてイラストや文章で紹介する
夏休み自由研究 社会編 まとめ
小学校高学年になると学校での学習内容も深まり、自分で本やインターネットを使って調べた内容をまとめたり発表する機会も多くなります。
国籍や性別の枠にとらわれない多様性への向き合い方やSDGsなど、保護者世代が子どもの時代より一層注目されるようになったテーマなども学習していることと思います。
社会をテーマにした自由研究は、夏休みの時間を使って学校での学びをより深めたり、地域社会とのかかわりやその中での自分たちの役割について考えるよい機会になると思います。
夏休みも残り約半分。参考にしていただけると幸いです。
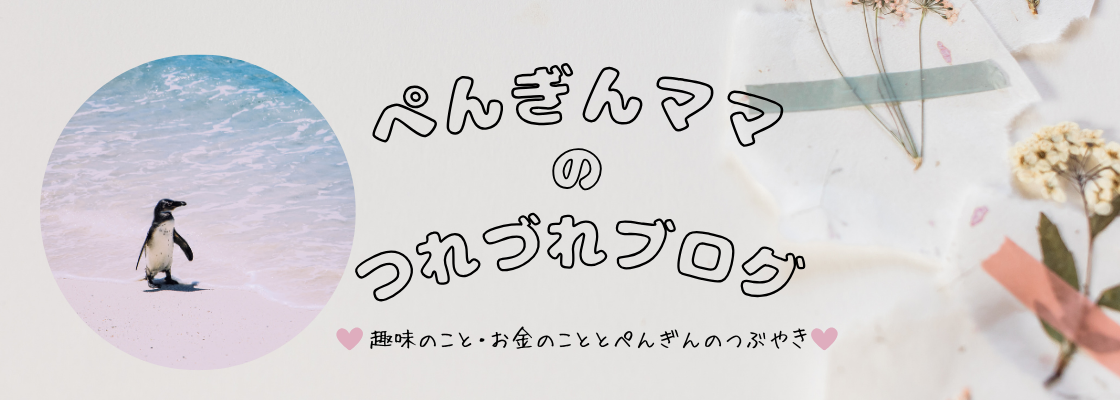
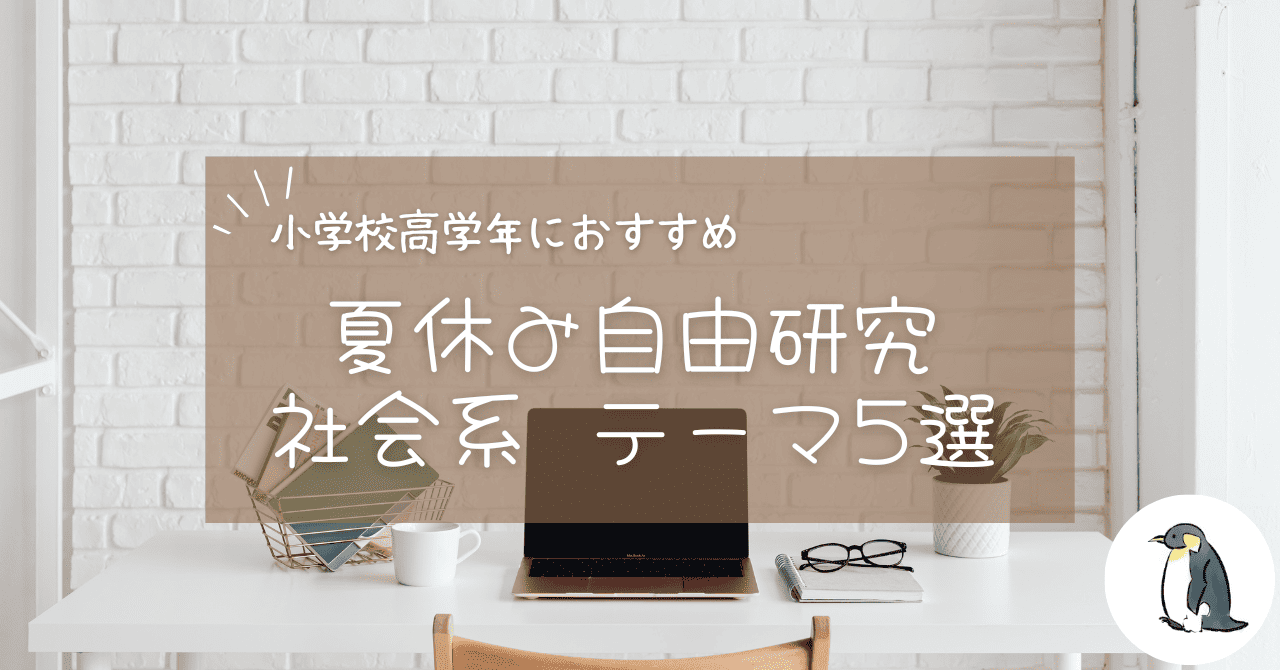
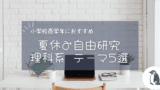

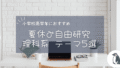
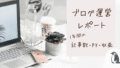
コメント