こんにちは、およげないペンギン、ぺんぎんママです。

小学生のお子さんをお持ちのお父さん・お母さん。
夏休みの宿題、順調に進んでいますか?
お子さんは宿題を計画的に進めるタイプでしょうか。また、ご自身が子どもの時はどうでしたか?
7月中にさっさと終わらせる?
計画的にコツコツと?
それとも夏休み終了間際に大慌てでやっつける?
夏休みの宿題の中で、子ども自身も保護者も、一番頭を悩ませるのが「自由研究」ではないでしょうか。
内容によっては1週間、2週間など期間が必要なものもあり、夏休み終盤になってから取り組むのは大変です。
まだ何をするか決まっていない場合は、8月前半のこの時期に取り組むテーマを決めて、計画的に夏休みを過ごしたいですね。
ぺんぎん家の次男も小6。
小学校高学年の自由研究テーマを「理科」バージョンでいくつかピックアップしてみました。
保護者目線で、大がかりな工作や難しく危険の伴う実験などはなく、できるだけ保護者の手伝いが不要なものを考えています。
自由研究のテーマ選びの参考になれば幸いです。
小学校高学年 夏休み自由研究テーマ
小学校高学年におすすめの自由研究テーマ5選を紹介します。
身近な不思議や「なぜ?」「どうなってるの?」の好奇心を掻き立てられそうな理科系のテーマを集めました。
レモン電池で電気の力を調べよう
レモン電池は、果物や野菜が電気を生み出す仕組みを学ぶのにぴったりです。レモンに銅板と亜鉛板を差し込むだけで、小さな電気が発生するのを観察できます。
レモンだけでなく、他の柑橘類やジャガイモなど、いろいろな食材で試してみましょう。それぞれの食材でどのくらいの電圧が出るかを測定し、比較すると面白いと思います。
必要な金属板や銅線がセットになったキットを使えば手軽に実験が始められます。また電子オルゴールやLEDなどがセットになったものもあり、実験の幅が広がります。
結果をグラフにまとめたり、写真付きで手順を記録したりすると、発表資料としても見やすくなりますね。
興味が深まればインターネットなどで「ボルタ電池」の原理を調べて、なぜ電気が生まれるのかを科学的に考察すると、より深い学びにつながります。
いろいろなスライムをつくってみよう
スライム作りは、手軽に化学反応を体験できる人気のテーマです。
お父さん・お母さんの中にも作ったことがある人は多いんじゃないでしょうか。
材料は100円ショップやホームセンターでも簡単に手に入り、スライム作りのキットもAmazonや楽天市場などで豊富に販売されているので、気軽に挑戦できます。
ホウ砂水と洗濯のり(PVA)を混ぜることで、液体が固体へと変化する様子を観察できます。
ただ作るだけでなく、どんな材料を使うとスライムの固さが変わるのか、色や感触に違いが出るのかを実験してみるのがおすすめ。
たとえば、
- ホウ砂水の量を変えてみる
- ホウ砂水の代わりに別の液体を使ってみる
- 洗濯のりに対する水の分量を変えてみる
- シェービングフォーム、ハンドクリームなど別の材料を加えてみる
- 食紅や絵の具で色を付けてみたりビーズなどを混ぜて見た目をアレンジしてみる
など、アレンジの幅も豊富です。
実験結果を記録する際は、材料・分量を正確に記載し、スライムの固さや伸びやすさ、数日後の乾燥状態などを考察してみましょう。写真を添えると視覚的にも分かりやすいレポートになります。
氷と塩で冷却実験をしてみよう
氷に食塩を混ぜると、温度がさらに下がる現象を実験します。
氷に塩を混ぜて温度がどれくらい下がるのかを、温度計を使って正確に記録しましょう。塩の量を少しずつ変えてみて、最も温度が下がる塩の量を見つける実験も面白いです。
他の物質(砂糖や重曹など)で温度変化が起こるのかも併せて実験してみてもいいですね。
またこの原理を利用して、氷と塩の冷却作用でアイスクリームを作ってみるのもおすすめ。材料を混ぜたとき、混ぜている途中(固まりはじめる前)、固まってアイスクリームになった時の温度などをグラフにしてまとめると、変化が目で見てわかります。
アイスクリームの作り方
1.材料(牛乳100ml・生クリーム100ml・砂糖20g)を小さな袋(ジップロックなど)に入れる(できるだけ空気を抜いてこぼれないようにしっかり密閉してね)
2.大きめのジップロックなどに氷と食塩を3:1で入れる
3.氷と食塩の袋の中にアイスクリームの材料が入った小さな袋を入れて密封する
4.タオルで包んで10~15分くらい上下左右に振り混ぜる
5.時々中身を確認し、とろみが出てきたらさらにしっかり振って好みの固さに仕上げる
☆お好みでバニラエッセンスやジャムなどを入れてもOK!
発展的なところでは、なぜ塩を混ぜると温度が下がるのかを調べてその科学的な理由までまとめると、この研究のグレードがぐっと上がります。
身の回りにある液体をpH試験紙で調べてみよう
酸性やアルカリ性といった水溶液の性質を、身近な液体で調べる実験です。pH試験紙を使えば、ジュースやお酢、石けん水など、様々な液体を簡単に調べることができます。
まずはpH試験紙の使い方をしっかり確認し、身の回りの様々な液体を調べてみましょう。たとえば、ジュース、お茶、水道水、石けん水、お酢など、種類をたくさん用意すると結果を比較しやすくなります。
調べた液体を「酸性」「中性」「アルカリ性」に分類して一覧表にまとめたり、色が変わったpH試験紙を台紙やノートに貼り付けたりすると、見た目にもわかりやすい研究になります。インターネットや本で、それぞれの液体の成分を調べてなぜその性質を持つのかを考えてみるのも面白いですね。
結晶作りに挑戦してみよう
ミョウバンや食塩などを使って、美しい結晶を作る研究です。水に溶かしたミョウバンを冷ますことで、キラキラした結晶が成長する様子を観察できます。結晶作りのキットも市販されています。
冷やし方やミョウバンの量などを変えて、どんな結晶ができるかを比べてみましょう。
- 水の温度:熱湯で作った飽和水溶液を常温でゆっくり冷やす場合と、冷蔵庫で急激に冷やす場合では結晶の大きさや形に違いはでるか調べる
- 溶かすミョウバンの量:水に対するミョウバンの量を変えて、どれくらいの濃さが一番大きな結晶ができるか調べる
- 水溶液を置く場所:風通りのよい場所と悪い場所、日当たりのよい場所と悪い場所などの条件でできる結晶の大きさや形に違いは出るか調べる
1日ごとなどに観察し、結晶がどのように成長していくかを記録したり、写真を撮ったりすると、研究の成果がわかりやすくなります。
小学生の夏休み自由研究 まとめ
実験によっては火を使うこともあるので注意が必要ですが、小学校高学年くらいだと材料さえそろえられれば一人でも進められる実験を5つ紹介しました。
市販のキットなども活用しやすい内容なので取り組みやすく、実験過程の写真や結果の表などでレポートにもまとめやすい内容になっています。
自由研究テーマ≪社会編≫はこちら↓
夏休みの自由研究はテーマ選びも大変で、ともすれば親が手伝わなければならないこともしばしば。
ギリギリになって「自由研究まだだったー!」となると親子いっしょになかなかの絶望です。
早めのテーマ選びで余裕をもって自由研究に取り組めるといいですね。
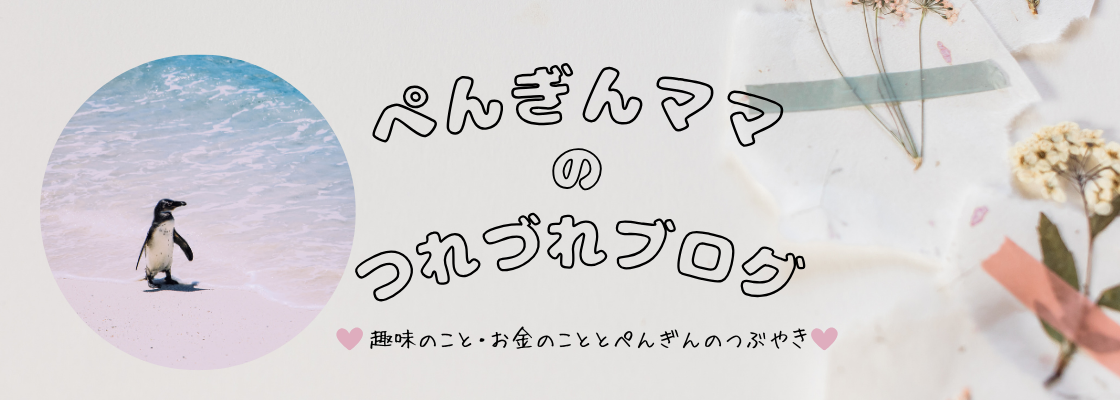






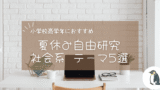
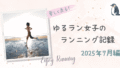
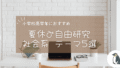
コメント